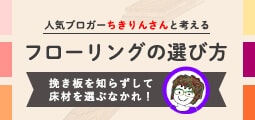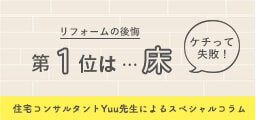床が生み出す「場」の力
建築家としてこれまで様々な空間を設計してきましたが、常に意識してきたのが「床」の存在です。建築の中で最も根源的であり、人にとってもっとも身近な要素だと感じています。床さえあれば、そこに「場」が生まれる。壁や屋根がなくても、人が立ち、歩き、座ることで、その空間は建築として立ち上がるのです。
床は、人の営みの出発点です。一見、何気なく通り過ぎる場所ですが、実は人間の身体が最も長く触れている建築要素であり、空間の本質が宿る場所だと考えています。
僕自身、北海道の自然豊かな環境で育ち、木に親しんできました。小学校2年のとき、無垢の木の床がある家に引っ越して、その温かみと広がりに自由を感じたのを今でも覚えています。
床は時間とともに生きる
20年ほど前、妻の実家を設計したときに木のフローリングを使いました。今でも帰省するたびに、そこに残る傷や擦れ、足跡のような痕跡が目に入ります。人の暮らしが静かに刻まれ、空間に深みを与えている。その変化を見ていると、「床は素材を超えて、時間とともに生きる存在なのだ」と実感します。
最近の床材は美しく、メンテナンス性にも優れています。それ自体は素晴らしいことですが、一方で、昔の木の床には、人工物では得られない「時間の積層」のような魅力がありました。木は「劣化」ではなく「変化」していく素材です。その変化に美しさを見いだすことができれば、建築との向き合い方も変わってくる。傷や擦れでさえ、そこに生きた人々の痕跡として、空間を豊かにしていくんです。
こうした考え方は、住宅だけでなく、公共建築でも同じです。たとえば、ある施設が50年後も使われ続けていて、かつて通っていた子どもが親となり、今度は自分の子どもと訪れる。そんな世代を越えた記憶が、床の上に積み重なっているとしたら、それはかけがえのない価値になるはずです。
床に残る痕跡が、未来への希望になる
僕はパリにも10年ほど事務所を構えていて、今も頻繁に通っています。ヨーロッパの街を歩いていると、「自分が死んだあともこの場所は残る」という安心感がある。そこにあるのは、痕跡が未来に残っていくという希望。床もまた、人の時間と未来をつなぐ、静かな媒介になれるのだと思います。
だからこそ、あらためて思うのです。床には、できる限り上質な素材を使いたい。そして、そうした素材を活かしながら、時間の経過を受け止め、なお魅力を増していけるような空間をつくっていきたい。そういう床がある建築は、やはり強いと思います。
大屋根リングに込めた想い
大阪・関西万博では、世界の多様な価値観が「ひとつの円」でつながる象徴として、大屋根リングを設計しました。そしてその屋上もまた、「床」として設計されています。直径約675メートル(外径)、円周約2キロにもおよぶリングの上を人が歩き、空を見上げ、地上を俯瞰する。そこは、空と世界をつなぐ「開かれた床」です。この床部分には、すべて国産の木材を使用しました。日本の豊かな森林資源と、木造建築の文化を背景に、木の持つ価値と可能性を世界へ伝えたいという想いを込めました。
夢洲に立ったとき、皆が口をそろえて言ったのが「空が広い」ということでした。その空の存在にかなうものはない。そう感じて、リングの中央をくり抜き、空を切り取るようなデザインにしたんです。人々が円環状の床に立ち、空を囲むように共有する。まるで空を持ち上げるような建築。それは、世界中の人々をつなげる象徴になると考えました。
空には国境がありません。その空を囲みながら、誰もが自由に歩き、交流する。そんな未来への希望が、このリングの床には込められています。


建築は未来への手紙
僕は建築を「未来への手紙」だと思っています。完成した瞬間が終わりではなく、そこから人々の営みが始まり、空間が育っていく。その積み重ねが、やがて「記憶」となって空間に残っていくんです。
そしてその記憶が、最も濃く刻まれるのが床だと思います。丁寧につくられた上質な床は、人々の人生に寄り添い、記憶を次の世代へと手渡していく器になる。公共建築でも住宅でも、床は「記憶の媒体」として、これからの建築に欠かせない存在になるはずです。